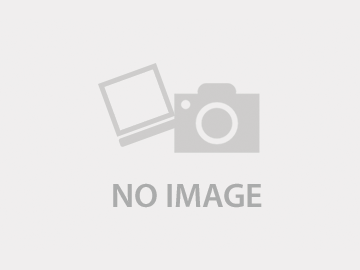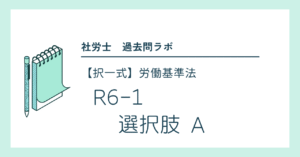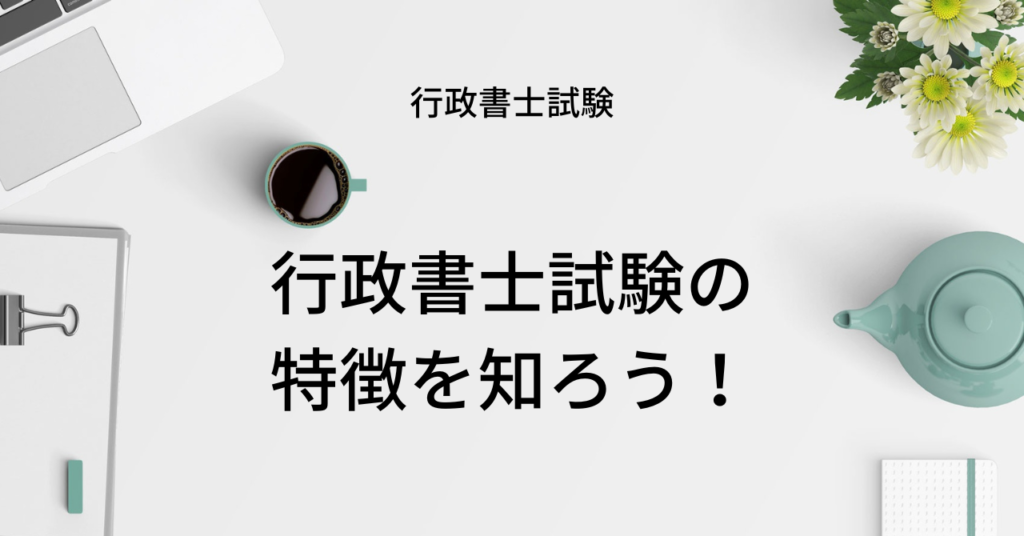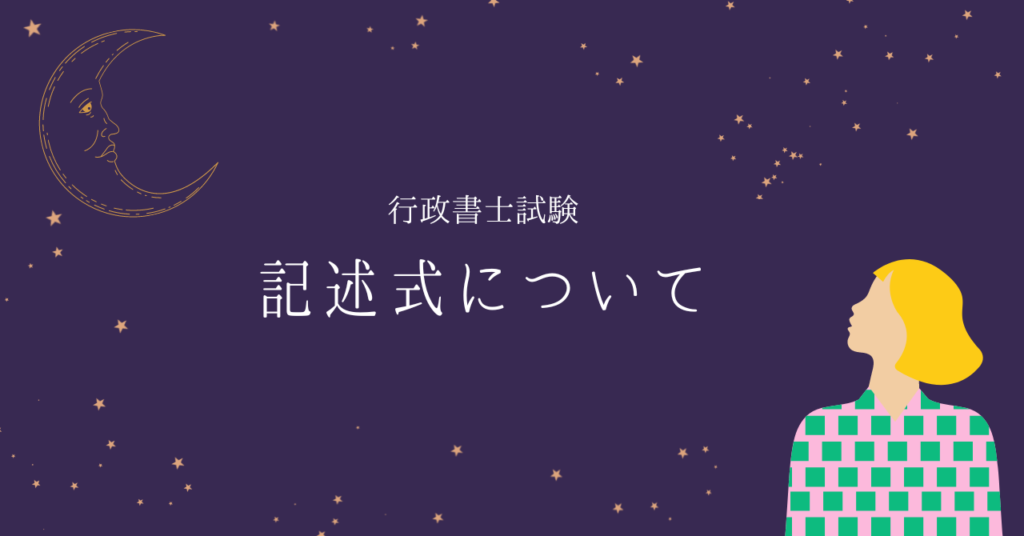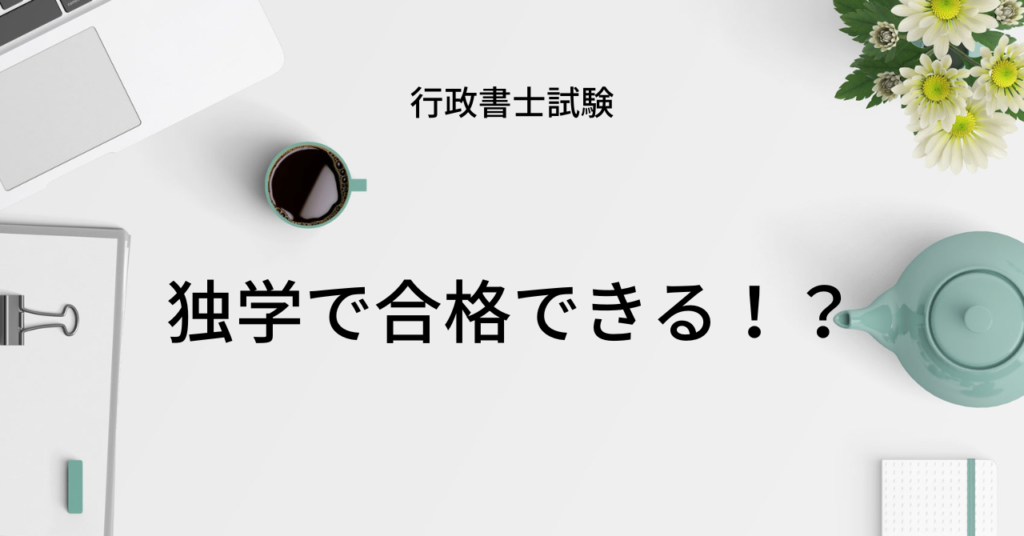試験問題 R6-1
法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
2 公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
3 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
4 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
ポイント
<重要ポイント>
・無効
<ポイント>
・未成年者(制限行為能力者)
・意思無能力
・公序良俗違反
・詐欺・強迫
・他人物売買
解答
解答は「1」です
選択肢ごとの解説
「→ p.〜」は、パーフェクト宅建士基本書(住宅新報出版)の参照ページです。
選択肢1
正しい
意思表示をした時に意思能力がなかった場合、法律行為は無効になります(民法3条の2)。
未成年者は制限行為能力者に分類されますが、今回の選択肢の場合、そもそも意思能力がなかったわけですから、制限行為能力者の検討をするまでもなく、民法3条の2により無効となります。
なお、営業を許された未成年者は、その営業に関する行為は法定代理人の同意なしに単独で行うことができる(法定代理人は取り消しできない)ことについても確認しておきましょう。
→ p.4
選択肢2
誤り
公序良俗に反する行為は絶対的に無効です(民法90条)。
無効については取消しのような追認の制度がありません。
そのため、当事者が合意していたとしても、その法律行為が有効になることがないのです。
→ p.16
選択肢3
誤り
詐欺・強迫による意思表示については、どちらも取消しの対象です(民法96条)。
問題文では、「詐欺の場合は取消し、強迫の場合は無効」となっていますが、強迫の場合も取消しであるため、誤りになります。
また、取消しがあると、はじめから無効となります(民法121条)。
ですので、詐欺に関する問題文に関しては正しいことになります。
→ p.11,21~22
選択肢4
誤り
他人物売買の契約は有効です(民法561条)。
他人所有の土地を売買の目的物にしても、その売買契約は有効であるため、前半部分が誤りとなります。
また、選択肢2の解説同様、無効の法律行為が有効になることもありませんので、後半部分も誤りです。
有効ではありますが、その他人の物を取得して買主に移転しなければなりません。
これができない場合、債務不履行責任を負うことになります。
→ p.140
コメント
難易度:普通
選択肢1に関しては少し迷うかもしれません。
意思能力と制限行為能力とでどちらの規定が優先されるんだろう、などと考えてしまうとなおさらです。
意思能力がなかったことの証明が難しいために制限行為能力という制度があります。
逆にいうと、意思能力がないことがはっきりしていれば、制限行為能力を考える必要がありません。
そういう意味では意思能力の規定が優先するともいえます。
民法で無効と規定されているもの(家族法は除く)
・意思無能力(3条の2)
・公序良俗違反(90条)
・心裡留保(93条)
・通謀虚偽表示(94条)
・条件の一部(131~134条)
このように、無効と規定されている法律行為は意外と少ないので、これを覚えてしまうというのも1つの手です。
無効の法律行為が当事者の追認等により有効になることはありません。
当事者が無効であることを知って追認した場合、新しい法律行為をしたものとみなされます。
ただこの場合でも、公序良俗違反などの強行法規に触れるときは、新しい法律行為とすることはできません。